写真を撮るとき、特にスナップ写真を撮るときにいちばん大事なことってなんだろう。
素晴らしい構図?
正確な色再現?
被写体のセレクト?
いや、違う。
それは「手ブレしないこと」と「ピントが合っていること」だ。
構図や色は、極論すればRAWデータを同時記録にしていればパソコンの現像ソフトを使って後からどうとでも変えられる。
でも手ブレしてしまった写真や、そもそもピントが合っていない写真はもう救えない。
どんなに優れた構図でも、しっかりとした色再現をしていても、「手ブレで輪郭がぼやけて」いたり「ピントが意図したところに合っていない」なら、まったく意味がない。
だからそれらを左右する「シャッタースピード」と「オートフォーカス速度・精度」はとても大切だ。
シャッタースピード

大阪駅
昔から言われている「手ブレしないシャッタースピード」の基準があるので紹介しておく。(絶対に手ブレしないということではない。)
「1/焦点距離(35mm判換算)」より速いシャッタースピード。
(「35mm判換算」ってなに、という人はこちらをどうぞ。)
初心者に普及しているAPS-Cセンサー搭載のカメラの場合、1/レンズの焦点距離×1.5倍。
iPhoneはだいたい28mmだ。
ぼくがよく使う「X100F」の焦点距離は23mm(1.5倍して35mm)なので、だいたい「1/40秒」以上のシャッタースピードなら手ブレのリスクをかなり減らすことができる。
…紹介しておいてなんだけど、この話は都市伝説みたいなものなので参考程度にしてもらいたい。
覚えてほしいのは、「可能な限りシャッタースピードを速くしたほうが、ブレない写真が撮りやすい」ということ。
広角レンズと望遠レンズでは、ブレずに撮影できる難易度が違う(広角レンズの方がブレにくい)とか他にも細かい話はあるけれど、とりあえずはこんな感じで覚えてもらいたい。
オートフォーカス精度・速度

伊勢神宮
さて、シャッタースピードは撮影者の努力でなんとかなる部分もあるけど、フォーカス精度・速度はどうだろう。
オートフォーカス(AF)が速くて正確なカメラを使うのが理想的だけど、必ずしもそうではない。
そういうとき、ピントが合う成功率を上げる方法がある。
レンズのF値(絞り値)を上げる。
(F値ってなに、という方はこの記事をどうぞ。)
F値が大きくなると、被写界深度(ピントが合う範囲)が遠近共に拡大する。
そうすると多少ピントが外れてもなんとかカバーできたりするものだ。
パンフォーカス(画像の手前から奥まで全てにピントがあった状態)に近い状態にできれば、失敗はぐっと減る。
具体的には、だいたいF5.6〜F8くらいに設定して、カメラのAF機能をしっかり使えば、被写体とその周辺にピントがあった写真が撮れると思う。
注意

兄
シャッタースピードとF値は露出(写真の明るさ)を決める重要な要素だ。
一般的にF値が小さいほど明るい写真になるし、シャッタースピードは遅い方が明るくなる。
なので、「ピント範囲を拡大するためにF値を上げると、シャッタースピードが遅くなる」し、「手ブレ防止にシャッタースピードを速くするにはF値を小さくしなければならない」。
具体的な数字を挙げてみると、
「シャッタースピード1/60、絞り値F8」の設定と同じ明るさの写真を、「シャッタースピード1/1000」で撮るためには、「絞り値をF2」にしなければならない。
(F値とシャッタースピードの関係についてはこちらをどうぞ。)
まとめ
そんなわけで「闇雲にシャッタースピードを上げても、F値を大きくしてもダメ」で、その辺は「いい感じのバランス」を見て設定する必要がありそうだ。
基本的にはシャッタースピードに気をつけるのがいいと思う。
スナップ撮影(広角〜標準レンズ)なら、「シャッタースピード1/640」くらいで感覚的に手ブレはかなり防げる(低速で歩いている人も止められる)。
でも一番いいのは、「たくさん撮って、自分のカメラで手ブレしない速さを覚える」こと。
それと、どうしても手ブレが心配なら、そもそも「手振れ補正機能が強い機種を買う」というのが実は一番の近道だったりする。
レンズ交換式カメラだと、ボディ内手振れ補正方式を採用しているソニーα7シリーズ(α7Ⅱ以降)やペンタックス、オリンパスあたりがオススメ。
コンパクトカメラにも手振れ補正付きのものは多いし、最近はスマホのカメラにも一部手振れ補正が内蔵されている機種がある。
結論:手振れ補正があるカメラを使う。
(ちなみに富士フイルムX100F、X-Pro2、X-T2いずれもボディ内手振れ補正はない…。)











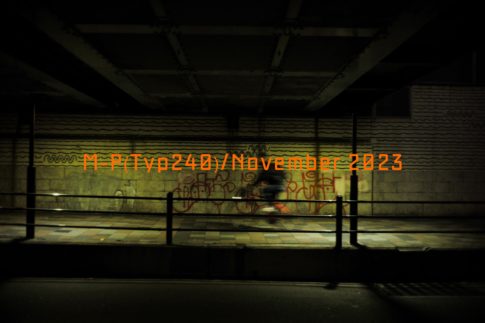





コメントを残す